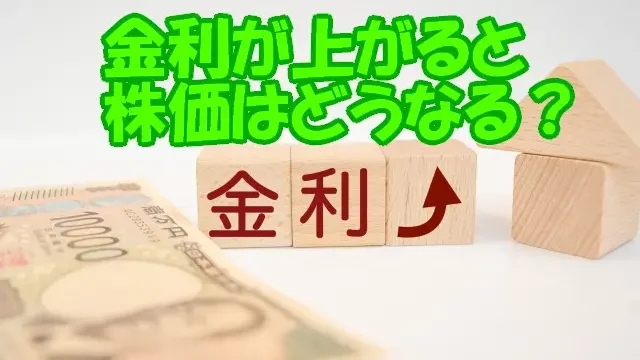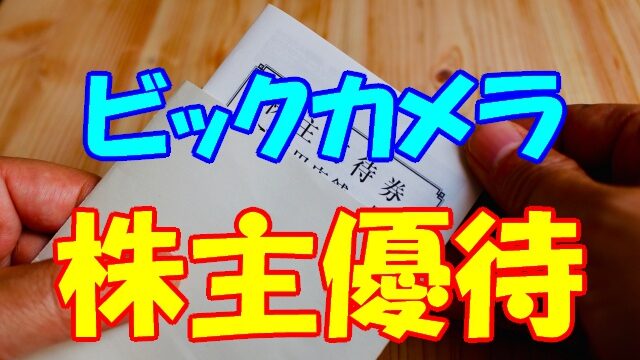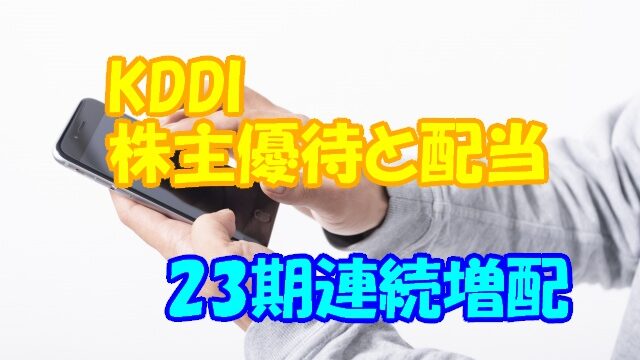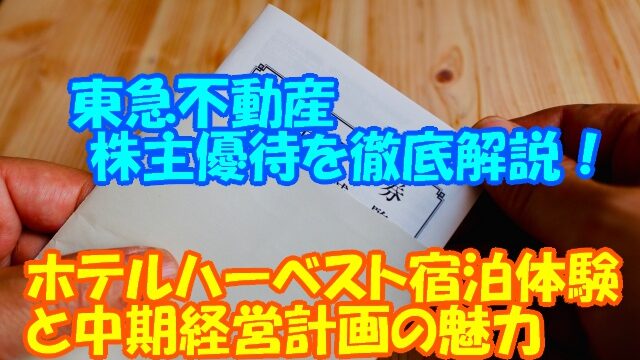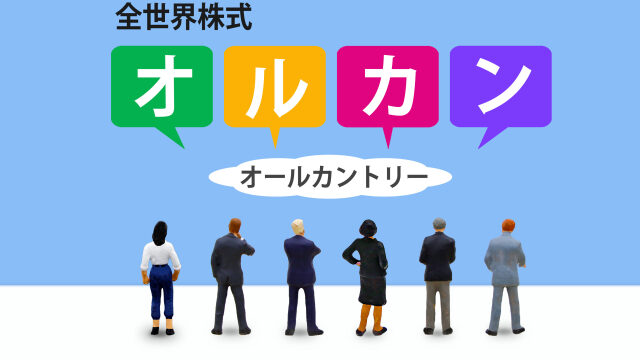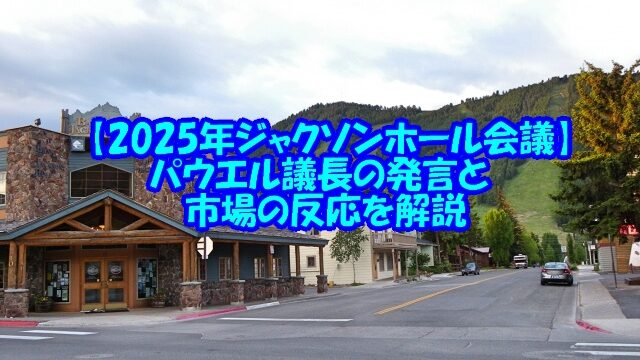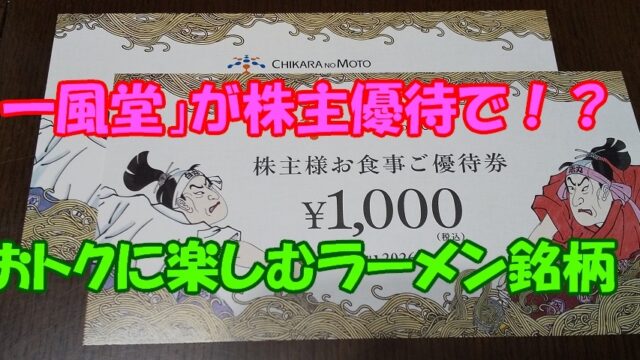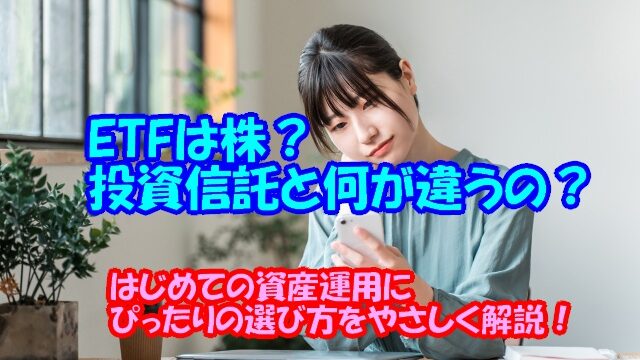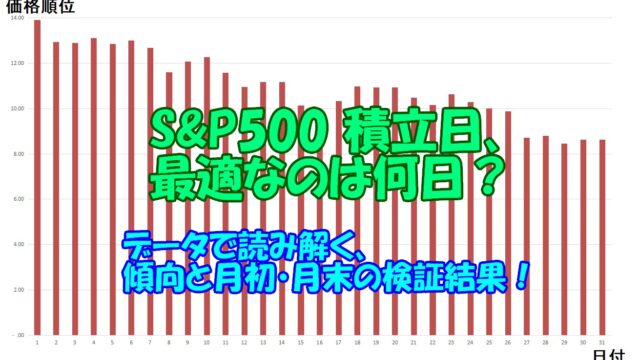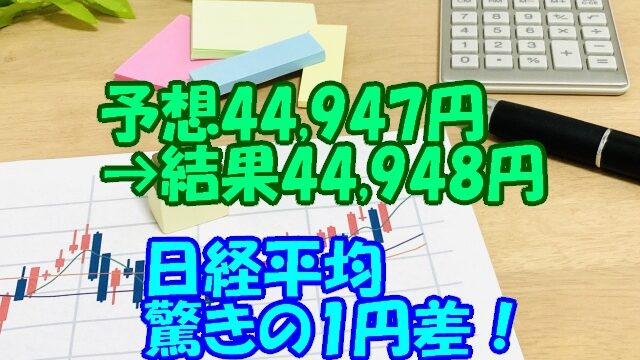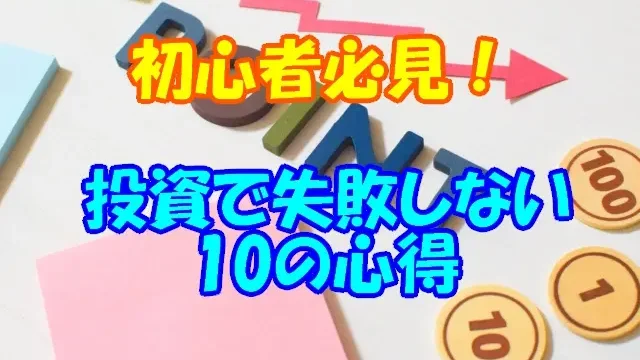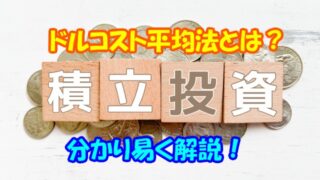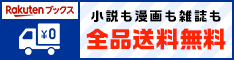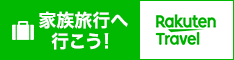インデックス投資の出口戦略 ~「定率売却」で資産を長持ちさせる方法とは?~
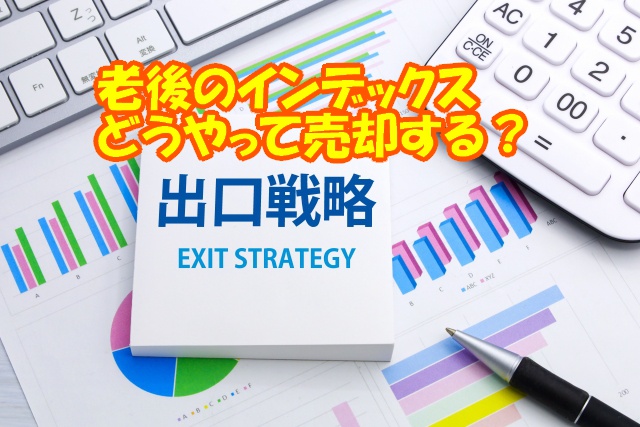
長期・積立・分散を基本とするインデックス投資は、多くの投資家にとって堅実な資産形成手段となっています。とくにドルコスト平均法を活用した定額積立は、市場のタイミングを気にせず投資を続けられるため、長期的には着実に資産を増やす可能性があります。
では、リタイア後などで収入が減少したとき、この築いた資産をどのように現金化していけばよいのでしょうか?
今回は、その出口戦略のひとつとして「定率売却」をご紹介します。
定率売却とは? ~資産を長持ちさせる仕組み~
「定率売却」とは、保有している投資信託などの残高に対して、一定の割合で定期的に売却していく方法です。例えば毎年4.8%(毎月0.4%)といった具合に、資産の一定割合を取り崩していきます。
この方法の最大の特徴は、売却額が資産の増減に応じて変動する点です。
定率売却の具体例
仮に資産残高が500万円あり、年間4.8%(月0.4%)の定率売却を行うとします。
- 初月:
500万円 × 0.4% = 20,000円を売却
→ 売却後残高:498万円 - 翌月(価格変動なし):
498万円 × 0.4% ≒ 19,920円を売却
→ 売却後残高:496万80円 - さらに翌月(基準価額が1%上昇):
資産残高:約500万9681円 × 0.4% ≒ 20,039円を売却
このように、資産が増えれば売却額も増え、逆に資産が減れば売却額も減るため、資産を枯渇させにくい仕組みとなっています。積立時のドルコスト平均法とは逆の考え方で、取り崩しの効率を高めることができます。
定率売却のメリットとデメリット
✅ メリット
- 資産残高が多いときには多く、少ないときには少なく売却するため、資産の減少リスクを抑え、資産の寿命を延ばす効果がある
- 過去の市場データ(1950年~2017年、年平均約10%のリターン)※を前提とすれば、年4.8%の定率売却でも資産は減らず、むしろ増えていく可能性がある
(※「ウォール街のランダム・ウォーク」バートン・マルキール著 より引用)
❌ デメリット
- 売却額が毎回変動するため、毎月一定の収入を求める場合には不向き
- 取崩し開始時から株価が下落し続けた場合は、取崩し時に一括売却するより受取総額が減る可能性もある
実際に使える証券会社のサービス
楽天証券の定率売却サービス
楽天証券では、投資信託の定期売却機能において「定率売却」が設定可能です。設定は0.1%単位で行うことができ、たとえば資産残高が523,863円で月0.4%を設定した場合、初回の受取金額は2,095円と表示され、直感的に分かりやすい仕様です。

また、運用利率の想定を入力することで、将来何年間資産が持つかのシミュレーションも可能です。売却率が年4.8%(0.4% × 12ヶ月)で、運用利率が年5%の場合は、資産が徐々に増えていく様子も確認できます。

SBI証券の今後の対応
SBI証券では現時点(2025年4月)で「定額売却」の機能は提供されていますが、「定率売却」は未対応です。ただし、2025年中の導入を予定しているとのことで、選択肢は今後さらに広がるでしょう。
まとめ:出口戦略としての定率売却は賢い選択肢
インデックス投資の積立で築いた資産を、引退後にうまく活用するには「減らさずに取り崩す」工夫が求められます。定率売却は、積立時のドルコスト平均法とは逆の考え方で、取り崩しの効率を高めることができ、長期的に資産を持たせる手段として非常に有効です。
市場の成長を信じる投資家にとっては、「定率売却」は将来の安心につながる出口戦略のひとつになるはずです。
インデックスの取り崩し「4%ルール」については、こちらで解説しています。
👉インデックス投資で築いた資産、老後はどう使う?──「4%ルール」で安心の取崩し術