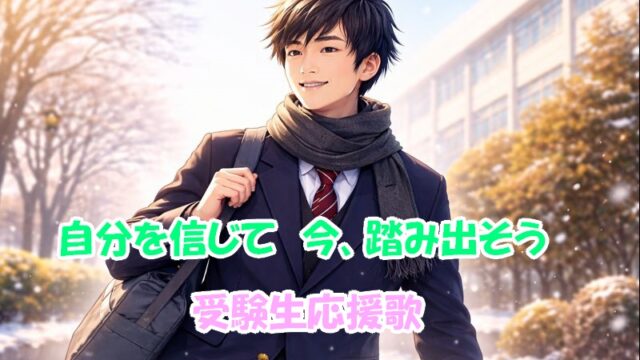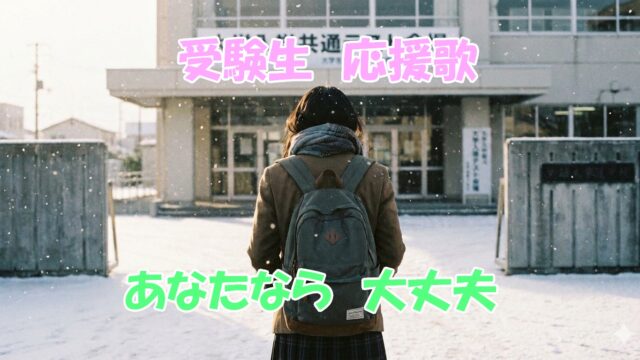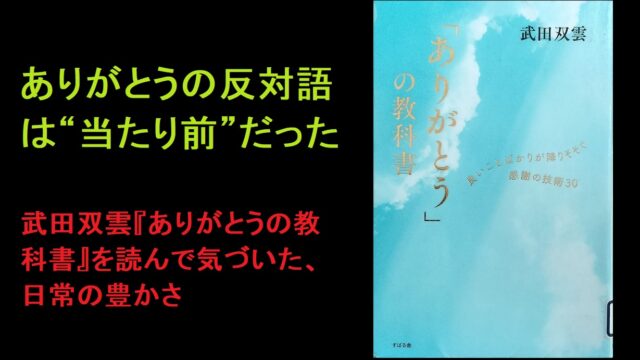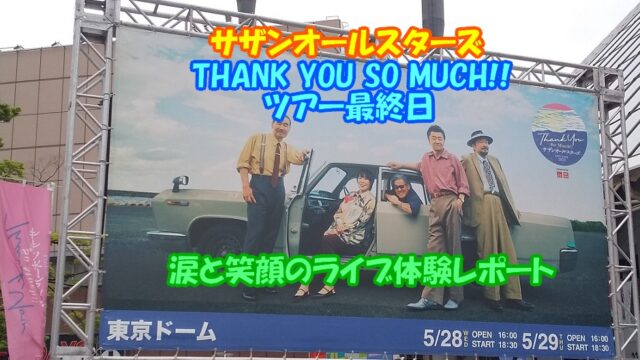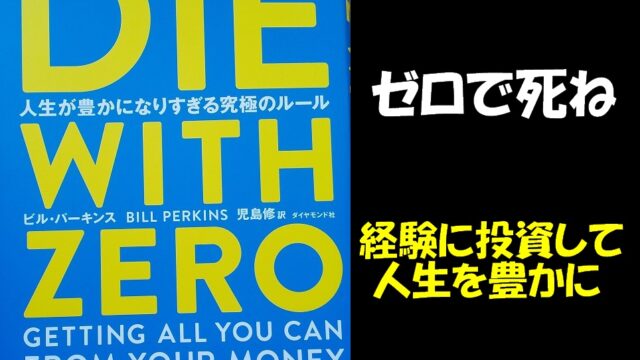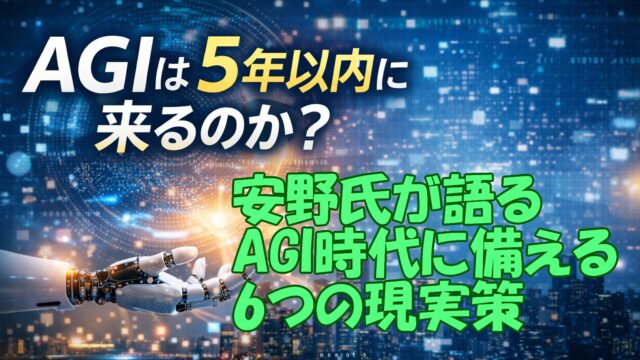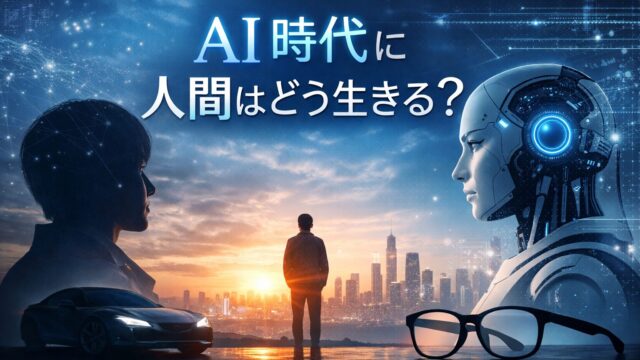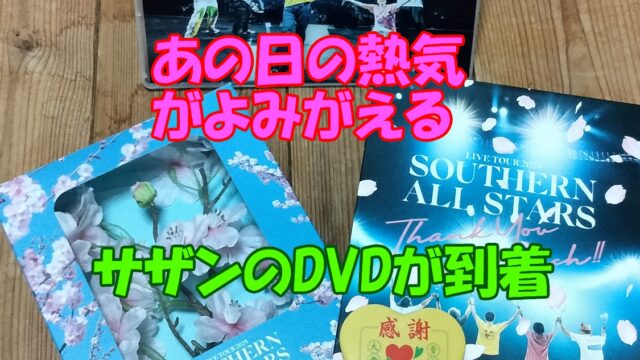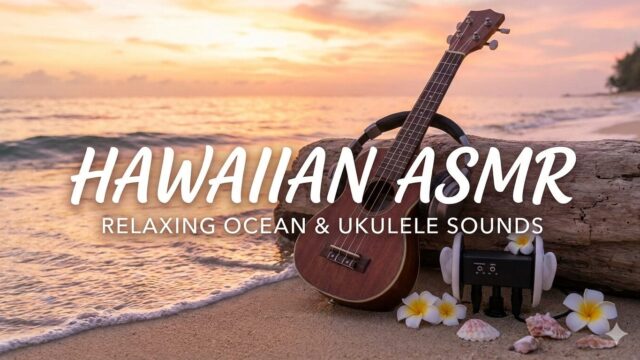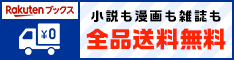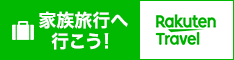先進医療特約とは?先進医療制度の仕組み、健康保険・高額療養費との関係から、加入の是非を考える
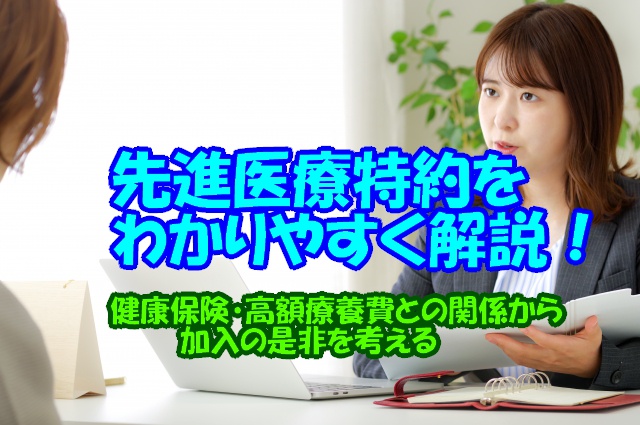
病気やケガは予期せぬタイミングでやってきます。そんな時に私たちを守ってくれるのが生命保険ですが、その中でも近年注目されているのが「先進医療特約」です。
テレビCMや保険のパンフレットでもよく目にする言葉ですが、実際にはどのようなものなのでしょうか。
今回は、先進医療制度の仕組みと、健康保険・高額療養費との関係を踏まえ、特約を付加する意味について整理してみたいと思います。
先進医療制度とは
「先進医療」とは、「健康保険法」の中でその定義を定めており、「将来、健康保険の適用に値するかを評価するため、厚生労働大臣が定めた療養」となります。
つまり、現時点では健康保険の適用外であるが、将来的には適用の可能性がある療養と定められたものとなります。
厚生労働省の「先進医療の実績報告(令和6年度:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」によると、次のとおりです。
・先進医療技術数:76種類
・実施医療機関数:449施設
・全患者数:177,269人
・保険外併用療養費の総額(保険診察分):約809.0億円
・先進医療費用の総額:約119.5億円
上記の「先進医療費用の総額」を「全患者数」で割ると、一人当たり平均で67,411円となり、保険で準備するよりも貯金で準備した方がよいようにみえます。
ただ、最先端のがん治療として注目されている陽子線治療や重粒子線治療は、1回あたり200万円から350万円程度かかるそうで、こういった高額の費用がかかる療養を目的とするならば、保険で準備する価値はありそうです。
医療費の負担については、健康保険の適用外であるため、技術料は全額自己負担になります。ただし、通常の診察や投薬、入院料などの“健康保険適用部分”については健康保険でカバーされます。
分かりずらいので、例で説明しましょう。
例:1ケ月の医療費合計300万円、そのうち先進医療の技術料が200万円の場合
(70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)の方の場合)
医療費合計300万円
うち先進医療部分(200万円):自己負担
うち通常の診察や投薬、入院料などの健康保険部分(100万円):
健康保険から支給:70万円(100万円の3割)
高額療養費として支給:約212,570円
自己負担:87,430円
→つまり、自己負担は、200万円 + 87,430円 = 2,087,430円となります。
※高額療養費の上限は、年齢や所得によって異なります
先進医療特約
生命保険や医療保険に付加できるオプションの一つが「先進医療特約」です。この特約をつけておくと、先進医療を受けた際にかかった技術料が保険から給付され、自己負担が軽減されます。
上記の例では、先進医療特約は、上記の200万円の自己負担の部分について支払い対象となります。
気になる保険料ですが、先進医療特約は比較的安価で、月々数百円程度に抑えられているのが一般的です。陽子線治療や重粒子線治療は、1回あたり200万円から350万円程度かかるそうで、こういった高額の費用がかかる療養を目的とするならば、保険で準備する価値はありそうです。
さて、先進医療制度の対象となる療養が変更されたら、保険料も変わるの? と不安に思いますよね。
「先進医療特約」の保険料は、加入時に決まったままです。
厚生労働省が先進医療リストを見直しても、その都度、契約者の保険料が増減することはありません。なぜなら、保険料は「保険会社が想定する先進医療の利用リスクを含めて」あらかじめ設定されているからです。
ただし、保険期間が満了を迎え、更新を行う際には、更新時に適用されている保険料となります。
メリットとデメリット
メリット
- 数百万円規模の治療費に備えられる
- 保険料は比較的安価で、万が一の時のコストパフォーマンスは高い
- 対象となる治療法はがん治療を中心に幅広い
- 対象となる治療は、厚生労働省が定期的に最新の療養に洗い替えてくれる
デメリット
- 実際に先進医療を受ける人は全体のごく一部
- 対象となる医療技術は厚労省の見直しで変わる可能性あり(例:白内障の「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」は2019年に先進医療から除外)
- 対応できる医療機関が限られる
加入を検討する価値はある?
結論からいえば、「加入しておく価値はある」といえるでしょう。
先進医療を実際に利用する可能性は高くないものの、陽子線治療や重粒子線治療などは、もし必要になった場合の経済的インパクトは非常に大きく、家計を直撃します。保険料が安価であることを考えると、“万一に備える合理的な特約”として位置づけられます。