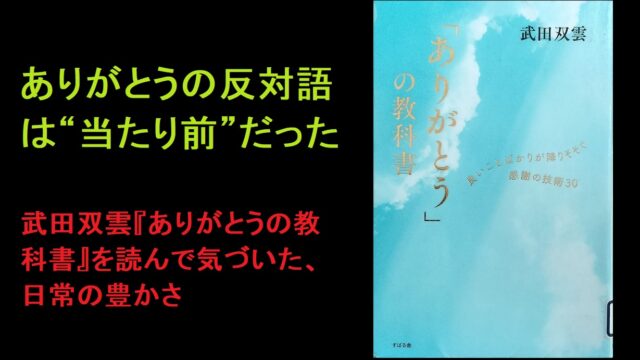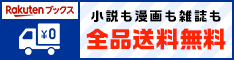あなたなら きっと大丈夫(受験生への応援歌)

受験は、ただの「試験」ではありません。
それは、一年、あるいはそれ以上の時間をかけて積み重ねてきた努力の集大成であり、
不安や涙、そして誰かの支えとともに歩んできた道のりそのものです。
模試の結果に一喜一憂しながらも、
それでも机に向かい続けた日々。
自信をなくしそうになったとき、そっと背中を押してくれた友達や先生、家族の存在。
今日はそんな受験生の一年を、
受験当日の朝という一瞬の情景に切り取り、”短編小説”、”オリジナル曲”として綴ってみました。
もし今、受験を控えている方がいたら。
そして、かつて受験生だったすべての方へ。
この物語が、
静かに勇気を届けるひとときになれば嬉しいです。
【短編小説 あなたならきっと大丈夫】
まだ夜の冷たさを残した空気の中で、彼女は玄関のドアを静かに閉めた。
東の空はうっすらと朱色に染まりはじめ、冬の朝特有の澄んだ匂いが肺いっぱいに広がる。
――今日は、受験当日。
足元のアスファルトは霜で白く、踏みしめるたびに小さくきしんだ音を立てた。
その音に合わせるように、胸の奥で心臓が静かに早鐘を打っている。
歩きながら、自然と視線が空へ向かう。
朝焼けの光が雲を縁取って、まるで新しい一日を祝うように広がっていた。
その光に包まれながら、彼女の心は、この一年をゆっくりとたどりはじめる。
春。
まだ肌寒い朝に、眠たい目をこすりながら机に向かった日々。
単語帳の紙は、何度もめくられて角が丸くなり、
数学ノートは赤ペンで埋め尽くされていた。
シャープペンの芯が折れるたび、ため息をつきながらも書き直した答え。
窓の外で鳥が鳴くころまで、机の明かりだけが部屋を照らしていた夜もあった。
「今日はここまで……」
そう呟きながらも、もう一問だけ、と問題集を開いた自分。
あの積み重ねが、この一年だった。
夏を越え、秋が来たころ。
模試の結果を受け取ったとき、紙の感触が妙に重く感じられた。
指先が少し震えながら、そっと開く。
――合格可能性、ギリギリ。
胸が大きく上下し、息が詰まるようだった。
「……あと少し。もう少し。」
でも、あの春から比べれば、確かにここまで来ていた。
帰り道の街路樹は赤く色づき、落ち葉が風に舞っていた。
その景色が、なぜか少し誇らしく見えたのを覚えている。
冬直前の最後の模試。
教室で配られた紙を見た瞬間、頭の中が真っ白になった。
――D判定。
数字の横に並んだ「30%前後」という文字が、冷たく胸に突き刺さる。
周りの友達の声がやけに大きく聞こえ、
自分だけが取り残されたような気がした。
帰り道、夕焼けが滲んで見えたのは、目に涙がたまっていたからだ。
「無理なのかな……」
誰にも聞こえないほど小さな声で、そう呟いた。
その夜、机に向かっても、問題が頭に入らなかった。
そこへ、スマホが震えた。
「結果どうだった?あんまり良くなかったか。でもさ、積み重ねてきたものは裏切らないよ」
友達からのメッセージだった。
しばらくして、先生からも声をかけられた。
「D判定は可能性がゼロじゃないってことだ。
君の実力なら、本番で発揮できれば、十分戦える」
家に帰ると、母が温かいスープを差し出してくれた。
湯気と一緒に、やさしい匂いが広がる。
「今回の結果が全てではない。ここまで頑張ってきたことは必ず身についているよ」
父も静かにうなずきながら言った。
「最後までやり切ろう。応援してる」
その言葉が、胸の奥でゆっくりと溶けていった。
――ひとりじゃない。
そう思えた瞬間、重たかった心が少し軽くなった。
それから彼女は、もう一度前を向いた。
朝はいつもより早く起き、
夜は眠くなるまで机に向かった。
間違えた問題には赤ペンで大きく丸をつけ、
できるようになるまで何度も解き直した。
不安は消えなかった。
それでも、手を止めなかった。
「できることをやろう」
その言葉だけを胸に刻んで。
そして、今。
朝焼けの中を歩きながら、彼女は深く息を吸う。
冷たい空気が肺に入り、心がすっと澄んでいく。
あの涙も、迷いも、
みんなの言葉も、温もりも、
すべてがこの胸の中にある。
足取りは自然としっかりしていた。
「行ってきます」
小さく呟くと、風がそれをさらっていった。
みんなのおかげで、ここまで来た。
みんなのおかげで、今日を迎えられた。
試験会場の建物が朝の光の中に見えてくる。
彼女は背筋を伸ばし、胸を張った。
不安はまだある。
それでも、それ以上に――
積み重ねてきた時間が、彼女を支えていた。
朝焼けは、静かに彼女の背中を照らしている。
その光の中で、彼女はまっすぐ、会場へと向かっていった。
【オリジナル曲 あなたならきっと大丈夫】
👇オリジナルの曲 にしています!